***
──夕暮れ時、雅は今までにも何度か来た柳の住む街の様子を目の端で捉えながら、目的地である彼女のマンションの前までやってくるとほっと胸を撫で下ろした。無事デートを遂行できたことに安心したようだった。傍から見ればいつも通りの余裕にも思える表情ではあったが、柳には雅の満足した様子が見て取れる。
「もうここまでで大丈夫ですよ」
「いや、玄関まで送ろう」
「ええと……それなら上がっていきますか?」
「?」
「デートを終えるには少し早すぎる時間でしょう? うちでお茶でもどうですか」
「………」
「蒼角は今日は外泊の日なので、ゆっくりしてくださって大丈夫ですし……」
「………………」
雅は少し考えたようにして口元に手を当てると、「それは」「送るというデートの最終行動が」「しかし」「ならば」と一人ぶつぶつと言っていた。そんな彼女に小首を傾げつつも、柳はエレベーターのボタンを押してしばし隣の狐シリオンの横顔を見つめていた。
十数秒後、やってきたエレベーターに乗り込むと柳は行き先階のボタンを押した。その間も雅は眉間に皺を寄せ何事か考え込んでいる。そんなにも考えることがあるだろうか、と柳は不思議に思った。もしかすると今日はこの後何か修行の予定でもあるのかもしれない。だとすればお茶に誘ったのは余計な一言だったかもしれないな、と柳は目を伏せた。
「──ここまで送ってくださってありがとうございました」
柳の声にはっとして、雅は顔を上げた。
目の前にはドア。
ここは柳の部屋だ。
「もう、着いてしまったか」
「ええ、着いてしまいましたよ。この後は修行でもあるんですか? 何か考え込んでいた様子でしたけど」
柳はそう言いながら鞄の内ポケットから部屋の鍵を取り出した。流れるように開錠すると、ドアを開けて雅を見る。
「お休みの日まで修行のことばかり考えるのは感心しませんけど……無理はしちゃだめですからね」
「ああ……修行の予定は、ないが」
「え?」
「いや、言うなれば今まさに修行とも言えるのかもしれない」
「?」
雅は一瞬視線を彷徨わせると、すぐに柳を見上げた。
「またデートに誘ってもいいか」
「えっ……と」
「……だめ、か?」
「いえ、もちろんいいです! あ、でも次はこんなにたくさん買っていただかなくて大丈夫ですからね?」
「むぅ……」
「大 丈 夫 で す」
「わかった……少しばかり、控えよう」
「ふふっ」
むすっとした雅の様子が可笑しかったのか、柳はくすくすと笑うと雅の頬を指先で撫でた。
突然のことに雅は驚き、文字通り目を丸くする。
「……なんだ?」
「いえ、困ったようなお顔が可愛らしくて。……すみません、こんなことして」
謝罪の意を表したのか柳はぺこり、とお辞儀をし、薄紅色の髪が揺れ落ちた。その拍子に眼鏡も少しズレ落ち、ブリッジを指で押さえながら柳が顔を上げようとした──瞬間だった。
──ガタッ
何か音がしたかと思えば、柳の背中に壁がトンとぶつかる。
一瞬の出来事で何が起きたのかわからなかった。
見れば目の前に雅がいる。
二人がいるのは玄関の内側。
ドアは今しがたバタン、と音を立てて閉じた。
「あ……みや、び?」
状況を整理すると、どうやら雅が柳の体を支えながら玄関の中へと入り込んだようだ。その証拠に、雅の手が柳の腰を抱いている。
「……昨夜デートについて予習した際、インターノットには他にも書いてあった」
突然の話題に、柳は一瞬頭の回転が遅れた。
腰に触れている手が気になって仕方がないが、何でもないことを装う為に笑顔を作る。
「あ……他にも、ですか? なんでしょう」
「家まで送ることについてだ」
「?」
「送り狼という言葉を、知っているか」
「………………?」
「だが私の場合は、送り狐になってしまうな」
「……えっ、あ……え?」
カチャン、と音が鳴った。
雅のもう片方の手が、鍵を閉めたのだ。
「みやびっ!?」
「柳、私は──
──次は恋人として、デートに行きたい」
柳の頬に雅の白い指先が触れる。
急に体温が上がったせいで、柳の口から熱い吐息が漏れた。
それを吸い込むように、雅の顔が近づいてくる。
「私はお前を誰よりも愛している。今までもこれからも、お前の隣に立ち、いかなる脅威からもお前を守ると誓おう」
「ま、待ってくださ……」
「この気持ちを伝えることはお前にとって負担になるだろうとは思っていた……だが私は、柳、お前が欲しい。──この身勝手さを許してくれるか?」
雅の吐息が、柳の唇にかかる。
「……んっ」
雅の口からは何か特別な息が吐き出されているのではないかと、柳は思った。彼女の息がかかる度、柳の体が甘く震え上がりそうになるのだ。この感情が一体なんなのか、自分に問うまでもないことはわかっている。
「……もし柳が許してくれるのならば、お前から私に口づけてほしい」
そう言って雅は自分の唇を、柳の唇へほとんどすれすれまで近づける。
少し動けば触れてしまいそうな距離。
柳はうるさく音を立てる心臓に急かされるようで──しかし理性をまだ手放そうとはしなかった。
「……み、やび」
「なんだ」
「ゆ、許す、許さない、ということではなくて、ですね……」
「む」
「まだ、その、ちゃんと私の気持ちを……伝えてないじゃないですか!」
「……柳は私が嫌いなのか?」
「違います!」
「では愛しているか」
「~~~っ!」
真っ直ぐな深紅の瞳が、柳を見る。
柳は目を逸らせずに、唇を噛んだ。
「その、か、課長のことは……ずっと見てきましたし、頼れる方だと思っています。もちろんもっと会議には出席してほしいと思ってますし、その面倒事から逃げる癖を直していただければもっと──」
「………」
「……すみません、その、違いますよね。だからその、今までは仕事上の大事なパートナーとして見てきて……だから今日のようにデートをしたり、触れられたりすると」
「?」
「多分これまで無意識に抑えてきた、気持ちが、溢れてしまうみたいで」
「………」
柳は潤んだ瞳で雅を見つめ、それから観念したように瞼を閉じると唇を優しく触れさせた。
「んっ……」
雅は少しの驚きの後、すぐに柳の首に腕を絡めて唇を強く押し付けた。
「ちゅ、ちゅっ……」
「……ん、ぷはっ……あの、雅」
「なんだ?」
「わ、私もその、貴方のことを、愛しているようです」
「ふむ、わかっている」
「!?」
「……この口づけからは、愛しい気持ちが直に伝わる」
「あ……うぅ……」
「柳、私も愛を伝えていいか?」
彼女の返事を待たず、雅は柳の唇にまた自身の唇を重ねた。
啄むような口づけを幾度もし、ふいに少し開いた柳の唇の隙間へ、雅の舌先がぬるりと差し込まれる。
舌先をつつき合うように触れさせると、雅は舌の付け根や上顎をざらりと撫でた。
「あっ、んむっ、ふ……はあっ……」
柳の目から涙が一筋落ちる。それに気づき、雅は唇を放した。
「嫌だったか」
「い、いや、ではなく、その……き、緊張で……!」
「緊張? そうか……私も同じだ」
雅はそう言うと、柳の手を取り自分の胸へと押し付けた。
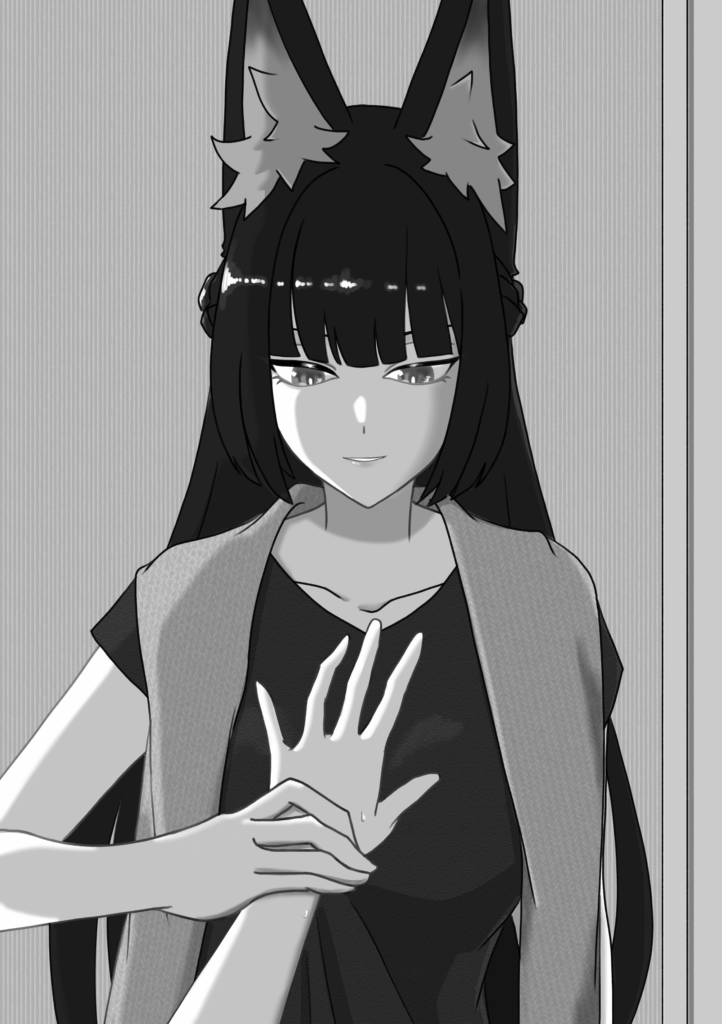
「……わかるか、心臓がこんなにも早打っている」
「……!」
「思えばデートに誘ったあの時から、ずっと私の心臓はこんな有様だ」
「えっ、ずっと緊張していたんですか?」
「ああ、ずっと緊張していた」
「……ふふっ、もう、雅ったら」
柳が優しく笑えばまるで周りに花びらが舞うようで、雅は胸がじんわりと温かくなっていくのを感じた。そしてそのまま、ぎゅ、と抱きしめる。
「……柳」
「雅、あの」
「む?」
「お茶を、飲んでいきませんか?」
「……そういえば、そういう話をしていたか」
「ええ、あのですから……もう少し、一緒にいられたら、と」
柳からの申し出に、雅は耳をぴくんっと反応させる。
表情こそいつもの無表情に近いが、口元にうっすらと笑みを浮かべて柳の鎖骨を彩る一粒ダイヤを撫でた。
「ならば、茶を淹れるのはしばし待ってくれ」
「えっ?」
雅はひょいと柳を抱き上げると、靴を脱いで部屋の中へと入っていった。
「ちょっと、雅……!?」
柳の僅かな抵抗など気にも留めず、そのまま彼女の寝室へと運んでいく。
整えられたベッドの上に困惑する柳を下ろすと、雅はまだ履かれたままの柳のパンプスを優しく脱がし──その足の指先にキスをした。
「っ!」
雅の手が、ワンピースから覗く柔らかな太腿をするりと撫でる。
柳はこの時思った。
明日から職場で会った時に、どんな顔でこの人に向かえばいいのかと。
そして今ならまだ引き返せるのではと。
だがしかし、頭の芯が麻酔でも打たれたかのように思考が停止していく。
頬を赤らませ、小さくため息を吐いた雅の表情に、息を呑む。
「──少し服を乱すことになるかもしれないが……どうか叱ってくれるな、柳」
ああ、
私は大変な人に愛されてしまった、
そう月城柳は思った。
そしてまた、
自分も同じくらいこの人を深く深く、愛してしまっているのだと
──甘い嬌声を上げながら気づいたのだった。
<了>

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます